【無料セミナー映像】キーワードから探る保育の奥深さ《第1講》テーマ:子ども理解(汐見稔幸先生)〈約50分〉
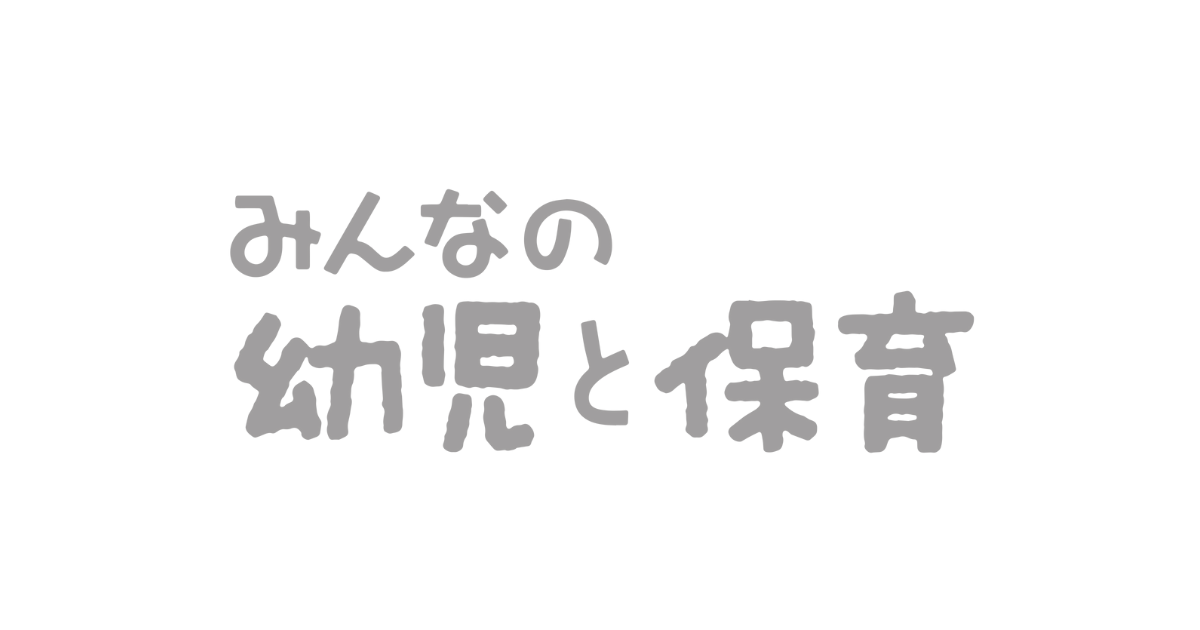
汐見稔幸先生による全12回のオンライン講座です。これからの保育で大切になっていくキーワードを入り口に、保育者として理解しておきたい保育の根本を探ります。第1講のキーワードは「子ども理解」です。
近年、「子ども理解」の重要性が保育現場で叫ばれるようになりました。しかし、その具体的な意味は十分に理解されているでしょうか。この講義で汐見先生は、「頑張らせる保育」の限界を指摘し、子どもの内面を理解することの大切さを説きます。
保育者には、子どもの行動の背景にある心の動きを想像し、適切に応答していく力が求められます。「アンダースタンド」という言葉の語源が示すように、保育者は子どもの自己生成を「下支え」する存在なのです。
ただし、一人の保育者の努力だけでは限界があります。子どもの面白い姿について語り合い、理解を深め合うことで、保育の質は向上していきます。また、子どもの多様性を認め、一人一人の特性に合わせた関わり方が求められます。
現代社会の複雑化する子育て環境の中で、保育者が子どもの味方となることが何より大切です。子どもの興味関心に寄り添い、その目が輝くような環境を整えることが、保育の使命なのです。
汐見先生のお話は、保育の原点に立ち返り、子ども理解の意味を問い直す貴重な機会を提供してくれます。子どもの心に寄り添う保育者を目指す方は、ぜひご視聴ください。

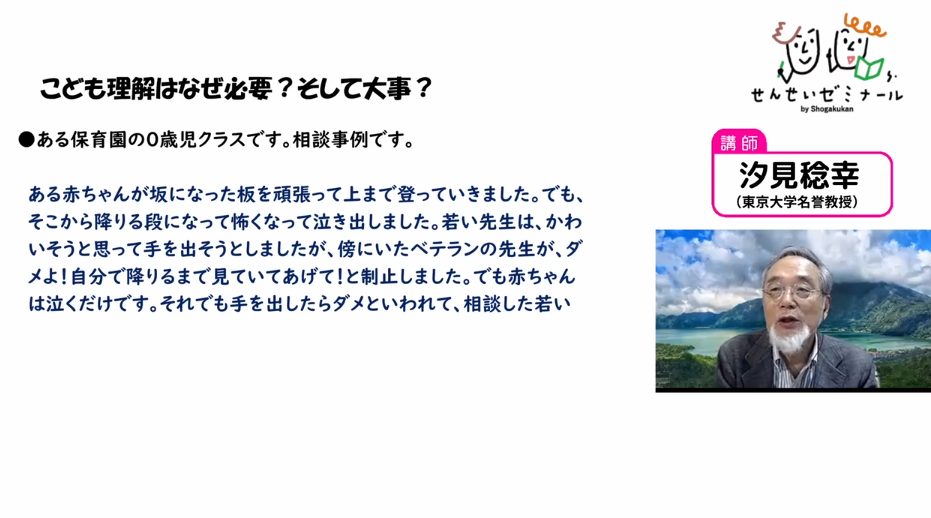
※2022年3月18日(金)にZoomで行った「小学館せんせいゼミナール」オンラインセミナーの録画より、前半の講義を切り出して構成しました。
お話のトピック
- なぜ「子ども理解」が重要なのか
- 自分で面白がってやった活動の重要性
- 子どもの行動のプロセスを重視する保育へ
- 保育者に求められる観察の視点
- 「理解」の語源と意味
- 保育者間の共通理解の必要性
- 子どもの多様性を認め、個に応じた対応を
- 現代社会における保育の役割
- 子どもの幸せとは何か

講師:汐見稔幸(しおみ・としゆき)
1947年大阪府生まれ。東京大学名誉教授、元白梅学園大学及び白梅学園短期大学学長。専門は教育学、教育人間学、保育学、育児学。


