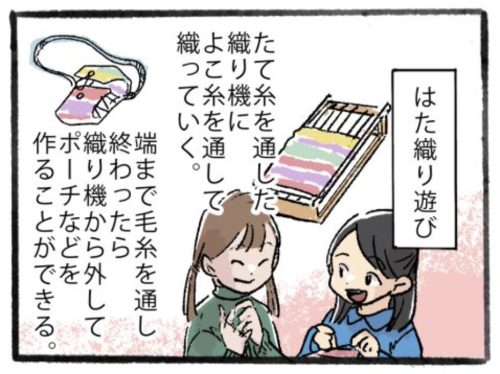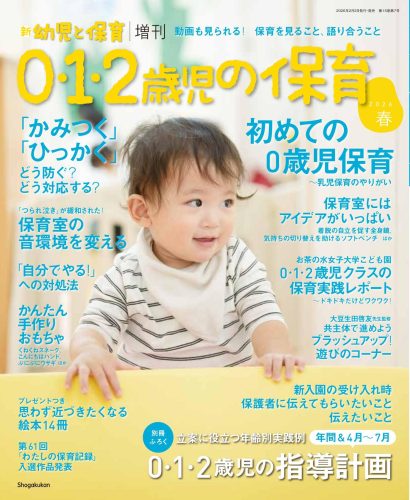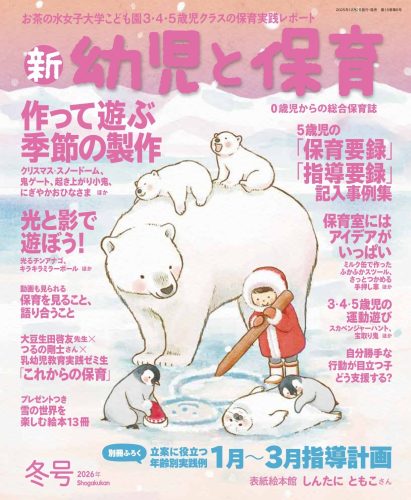「塗り絵だけ」の活動に違和感が…【保育マメマメQ&Hints! with 大豆生田啓友先生】


大豆生田 今回の質問は、「園では、塗り絵のコピーがたくさんあって、そればかりやらせています。どうしたらいいのでしょうか?」です。答えはひとつじゃありません。ぼくの考えるいくつかの対応例をあげます。みんなで対話して、考えていきたいですね。
※公式Instagramで今回のテーマの動画(約90秒)が見られます。(←文字をタップorクリックしてください)。右下は、リール動画撮影中の様子(写真左は小学館編集スタッフ)
大豆生田啓友先生
玉川大学教授。保育・子育て支援などが専門。特に保育の質の向上が研究のメインテーマ。著書に『日本が誇る! ていねいな保育』『日本版保育ドキュメンテーションのすすめ』(ともに共著・小学館)、『子どもが中心の「共主体」の保育へ』(監修・小学館)など多数。最新刊は、『保育の「ヘンな文化」そのままでいいんですか!?』(柴田愛子先生との対談集・小学館)。
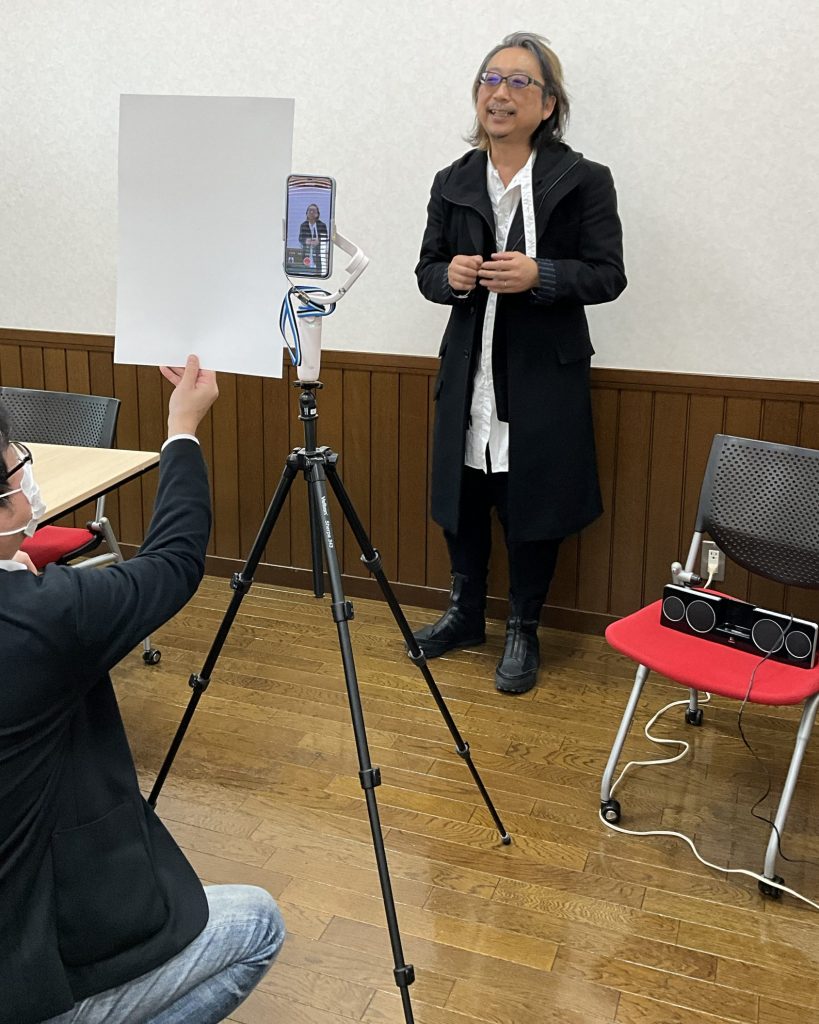
保育は、子どもの生活に丸ごとかかわるお仕事。
そして、同僚や保護者との関係も複雑に交ざり合って、
なかなか個人の思ったとおりにはいきません。
「こんな場合、どうしたら?」
そんな現場の保育者が抱える悩みや疑問に対して、
大豆生田啓友先生から、考え方のヒントをいただきました。
これをもとに、仲間とぜひ話し合ってみてください。
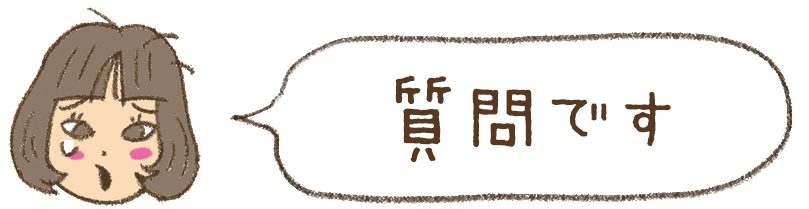
Q美 転園してきた園で、ほとんど絵画系の遊びをしていません。絵を描く紙も1日ひとり1枚と決められています。
でも、塗り絵のコピーはたくさんあって、そればかりやらせています。もっと、好きに描画活動をさせてあげたいのですが、どう伝えたらいいですか?
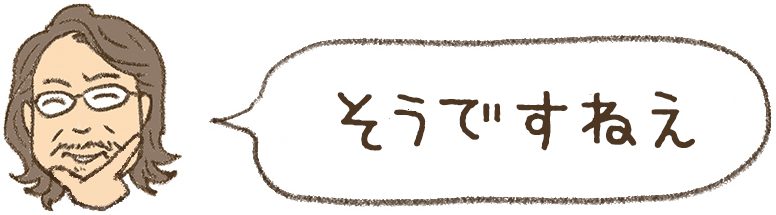
目次
「塗り絵」にこだわる理由は?
マメ先生 そもそも、なぜ園の先生たちが塗り絵にこだわっているか、ですよね。
●塗り絵は型に色を塗るだけなので、手軽に始められるから。
●塗り上がれば完成するので、達成感が得やすいから。
●線の内側を塗るというルールがあるので、画材をうまく使えるような巧緻性が高まるから。
●塗り絵で、色味、配色のデザイン力が養われやすいから。
このような導入やスキルアップに関係する理由ならまだ分かりますが、
■好きなキャラクターの塗り絵を渡せば、おとなしくしていてくれるから。
■子どもにはちゃんとした絵が描けないので、塗り絵以外は意味がないと思うから。
こんな大人目線の事情でほぼ「塗り絵一択」になっているなら、ちょっと考えてしまいますね。
確かに、低年齢のクラスや入園したてのときは、塗り絵はとっつきやすくていいと思うんです。そうだとしても「そればっかり」になるのは避けたいところです。
大人の教育的な望み、期待を超えて
マメ先生 大人が望むような人や物の描画や、画材の使い方を期待しなければ、子どもはいくらでも好きに表現するものなんです。色鉛筆でいろんな色を試し書きしたり、クレヨンでトントン紙をたたいたり、サインペンで爪を塗ったり。
こういう活動は、すべてその子にとって価値があります。見ていればわかりますが、そうやってその画材の可能性を楽しみながら探索しているんですよね。
私たち大人だって、初めての道具を与えられたら、使う間に試してみようと思うのでは? 経験の少ない小さい子なら、なおさらです。
スキルなどの上達も、それはあくまで自由な活動の「結果」、身についてくればよくて描画は、まず、本人が楽しむための活動と考えるのが自然ですね。

自由さの中で、育つものこそ
マメ先生 紙や画材はやはり、自分の思ったとおりに使って、「好きに表現していいよ」という態度で渡すのがいい。そこに塗り絵が混じっていても構いません。塗り絵もやりたい子が選ぶのであれば、それは自由な描画活動になります。
表現の自由の保障は、「子どもの権利条約の第13条」にも書かれています。そういう自由さの中で、子どもはその子らしい感性や、創造性、意欲を育てていくんですよね。
紙もできればいろんな種類、大きさを用意してあると、モチベーションが上がります。いつもA4のコピー用紙や、定形の画用紙である必要はないと思います。家庭から不要なノートや、包装紙などを、持ってきてもらうよう呼びかけてもいい。できるだけ好きな紙に、好きな画材で、好きなように描く。
「自由な表現を大切にすること。それはその子そのものを大切にすること」。そう考えて、その子の表現も尊重してほしいですね。
今回のマメマメヒント

★この記事は、小学館『新 幼児と保育』公式Instagram(←こちらをタップorクリック!)でリール動画を配信した内容にweb版として加筆・再構成したものです。また、小学館の雑誌『新 幼児と保育』では、ほかのリール動画で配信した内容に加筆・再構成し掲載していますので、どうぞご覧ください。また、このコーナーへの質問、疑問も募集中です。下から投稿できます。
お話/大豆生田啓友(おおまめうだ ひろとも)先生
玉川大学教授。保育・子育て支援などが専門。特に保育の質の向上が研究のメインテーマ。著書に『日本が誇る! ていねいな保育』『日本版保育ドキュメンテーションのすすめ』『子どもが対話する保育「サークルタイム」のすすめ』(ともに共著・小学館)、『子どもが中心の「共主体」の保育へ』(監修・小学館)、『保育の「ヘンな文化」そのままでいいんですか!?』(共著・小学館)など多数。
構成・イラスト/おおえだ けいこ
【関連記事】
保育マメマメQ&Hints! 保育の悩み、立ち話 with 大豆生田啓友先生シリーズはこちら!
・幼保小連携ってどうしたらよいのでしょうか?【保育マメマメQ&Hints! with 大豆生田啓友先生】
・発達がゆっくりな子がほかの子と遊べません。どうしたらよいでしょうか?【保育マメマメQ&Hints! with 大豆生田啓友先生】
・「お客様保育」に疑問を持っています。どうしたらよいでしょうか?【保育マメマメQ&Hints! with 大豆生田啓友先生】
・絵本の園内研修のやり方について教えてください【保育マメマメQ&Hints! with 大豆生田啓友先生】
・「塗り絵だけ」の活動に違和感が…【保育マメマメQ&Hints! with 大豆生田啓友先生】
・「こども誰でも通園制度が不安です」【保育マメマメQ&Hints! with 大豆生田啓友先生】
・「業務改善がうまくいきません」【保育マメマメQ&Hints! with 大豆生田啓友先生】
・「男性保育士に戸惑いがあります」【保育マメマメQ&Hints! with 大豆生田啓友先生】
・「パソコンが苦手で困っています」【保育マメマメQ&Hints! with 大豆生田啓友先生】
・「園で待ち時間などに子どもにビデオを見せたくないと思っています」【保育マメマメQ&Hints! with 大豆生田啓友先生】
>>もっと見る