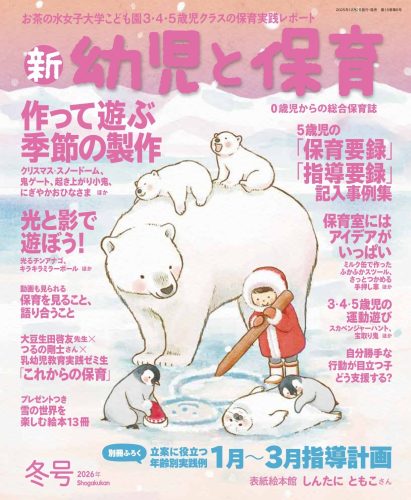大豆生田啓友先生✕つるの剛士さん|注目園訪問レポート「地域全体で子どもの成長を楽しめる社会へ」


大豆生田先生と、幼稚園教論二種免許・保育士資格を持つタレントのつるの剛士さんが、今回訪れたのは埼玉県久喜市にある「学校法人柿沼学園認定こども園 こどもむら」。地域全体で子育てをサポートする仕組みを見学しながら、未来の保育のあり方を考えます。
※取材時に撮影した動画(約40秒)が見られます。(←タップ or クリック)

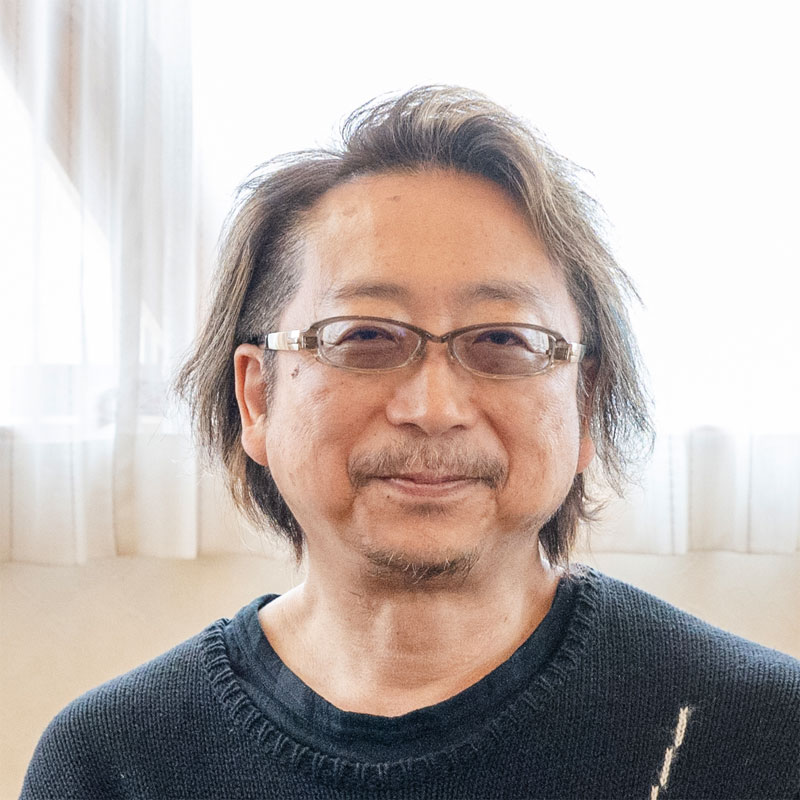
玉川大学教授・大豆生田啓友先生
1965年、栃木県生まれ。玉川大学教育学部教授。保育の質の向上、子育て支援などの研究を中心に行う。NHK Eテレ『すくすく子育て』をはじめテレビ出演や講演など幅広く活動。著書に『日本が誇る! ていねいな保育』(共著・小学館刊)など多数。

タレント・つるの剛士さん
1975年、福岡県生まれ。『ウルトラマンダイナ』で俳優デビュー。音楽でも才能を発揮し人気に。2男3女の父親。2022年に幼稚園教論二種免許、保育士資格を取得した。著書『つるの家伝統・見守り育児 つるの恩返し』(6月25日発売)。
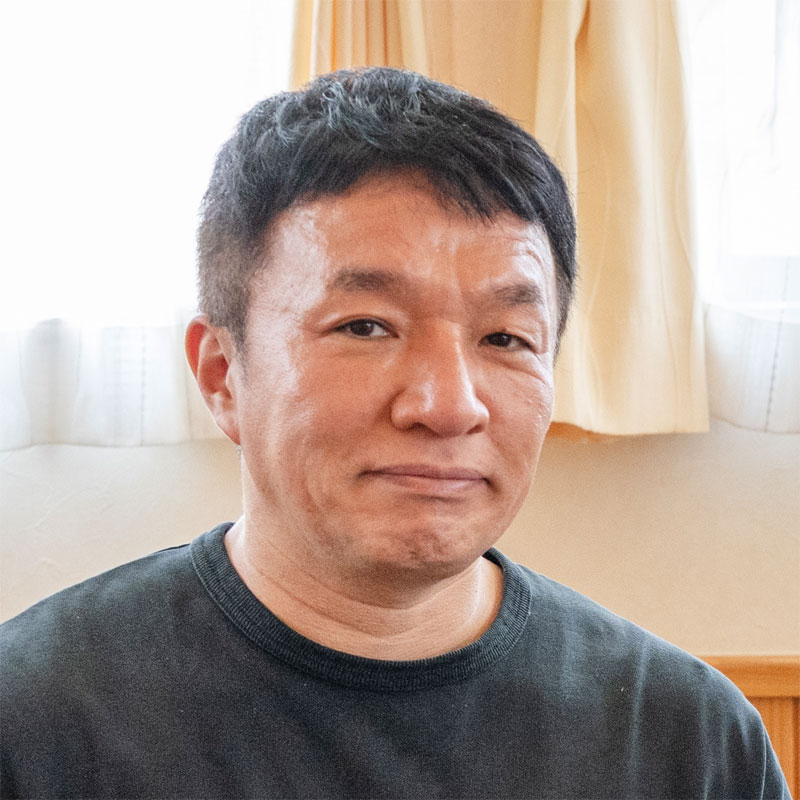
学校法人柿沼学園 認定こども園 こどもむら理事長・柿沼平太郎先生
祖父が1975年に設立した幼稚園を受け継ぐ。2012年に認定こども園こどもむらを設立。ほか学童クラブや児童向けの学習支援施設など多数運営し、地域に独自の子育て文化を築き貢献。
目次
学校法人柿沼学園認定こども園こどもむら(埼玉県・久喜市)
訪問ドキュメンテーション
埼玉県久喜市伊坂の閑静な住宅街にある学校法人柿沼学園認定こども園「こどもむら」は、地域の子どもや保護者を支える施設を多数併設する園。目標として掲げるのはシンプルに「子どもが増えて地域全体が活性化すること」。その成功例ともいえる取り組みを取材しました。
街と子どもをつなぐ環境づくり
こどもむらは、昭和50年(1975年)設立の「栗橋さくら幼稚園」がルーツ。認定こども園こどもむら、栗橋さくら幼稚園を中心に、小規模保育所、企業主導型保育所、学童保育所などを運営。ほかにも、子育て支援センター、放課後児童クラブ、マタニティーサポート、家庭訪問型サポート、親子で集えるカフェや駄菓子屋さんなど、子どもや子育て世代の親たち全般を支援する取り組みを続けています。
それほどたくさんの施設を運営する理由は、地域すベての子どもが幸せに暮らせ、子育てに不安を抱く親たちが安心して住み続けられる街にするため。「ひとりでも多くの子どもを増やしたい」と、園にとどまらず、施設を地域に開放。結果、持続可能な社会が根づき、子どもも増えて街が活性化したのだといいます。
「街のあちこちで、保育者さんが子どもたちを連れている姿があって、こんなに子どもがいる環境は最近なかなか見ませんよね。まさに名前のとおり『こどもむら』。すごいなあ、この取り組み!」と、つるのさん。
「少子化で幼稚園の存続すら危ういといわれている社会の中で、子どもも施設も増えているというのが驚きです。ここで行われている地域に根ざした保育や子育て支援は、少子化対策の可能性を見いだすモデルケースになりますね」と、大豆生田先生は言います。


地域の子どもと、子育て世代の大人たちを支える施設
大豆生田先生とつるのさんは、こどもむらが運営するさまざまな施設を見学しました。まず訪れたのが「カフェ」と駄菓子屋さんの「むすび堂」。カフェは親子で一緒にのんびり過ごしたり、保護者同士がつながる場にもなるコミュニティー施設。子どもに無料で食事を提供する日を設けるなど、子ども食堂としても機能するそうです。「むすび堂」は、子どもたちの情報交換の場所。店員も大人ではなく学童クラブの子が務める日もあります。大豆生田先生とつるのさんは、子どもたちから説明を受けながらたくさんのお菓子を買っていました。
次に訪れたのが、産前産後の支援「マタニティーサポート」を行う施設「にじいろのおうち」。こどもむらの理事長、柿沼平太郎さんが特に力を入れている無料の施設です。離乳食、ベビーマッサージ、ヨガなど妊婦さんに寄り添ったさまざまな講座を実施。不安を抱える妊婦さんが子育てについても気軽に相談できる場として提供しています。自ら5人の子どもを育てるつるのさんも共感をもってこう言います。
「特に移住してきた人とか、近隣に知り合いがいない妊婦さんとかは相談できずに不安を抱えている人、結構多いと思うんですよ。おなかが大きいうちに頼れる場所があるってとても重要ですよね。親の気持ちが安定すれば、子育ても穏やかにできるし。しかも無料の施設でしょ。妊婦さんがここに住みたくなって子どもが増える理由、わかりますね」
「地域の子どもや親たちが、これらカフェや支援施設などのネットワークを利用して穏やかに過ごすことが、結果的には家庭や学校の風土にもよい影響を与えるんじゃないでしょうか。社会全体が、”穏やかな気持ちの中でつながる“ということがとても重要ですね。持続可能な保育のあり方を、改めて考えさせられました」(大豆生田先生)





【鼎談】
子どもを取り巻く環境と保育の役割
少子化が進む社会の中で、園が生き残るためには何をすべきか――。そんな保育の課題に長年取り組み、ひとつの可能性を見いだした認定こども園「こどもむら」。見学を終えた大豆生田先生とつるのさん、こどもむら理事長の柿沼平太郎さんが、子ども中心の社会にするために何が必要か、保育の役割を考えます。

大豆生田/こどもむらは、ひとつの幼稚園から始まって、目の前にあるいろいろな課題に対して「今、何ができるか」を模索しながら、いろいろな取り組みをされてきた園。少子化が問題視される社会の中で、保育の場が拠点となって地域の子育てをサポートしていくと、やがて街全体が子供中心の社会に変わり、子どもも増えていく。これからの日本の保育のあり方を考えるときに、とても重要なモデルになると、改めて思いました。
つるの/最初からフレームがあるわけじゃなくて、「子どもを増やす」というシンプルな目的のためにゼロからつくり上げたところが、めちゃくちゃ夢あるな〜って思いました。まるで街の中で必要なものをちょこちょこ増やして運営していく『シムシティ(街をつくり運営するゲーム)』。すごく憧れるけど実際に運営するとなると壁が多そうで後ずさりしちゃうけど、ここを取材して「こんな夢のようなことが実現できるんだ」って、いろいろな可能性を感じ取れて、すごく勉強になりました。
柿沼/もともとこの地域は田んぼと里山で、何もなかったからできたのかもしれません。僕は20年ぐらい前に理事長になったのですが、そのころは200人定員の幼稚園に100人しかいなくて、廃園か休園を考えていたんです。だけど祖父がつくったものを残したくて、試行錯誤のスタートでした。最初は保護者のニーズに合わせた教育のようなものをやっていて、3年ぐらいで園児数180人ぐらいに回復したんです。だけど、「何か違うな、この教育では子どもにとってよくないかな」って思うようになって。以後、幼児教育や保育を学んで、今のような親子をサポートできるような施設を、まさにシムシティのように少しずつ、つくっていったんです。
大豆生田/特に産前産後のサポートは素晴らしいですね。国や自治体から補助を受けているのではなく、自主事業としてされているというところに感銘を受けました。赤ちゃんを幸せに産み育てることが、その先の子どもの教育や社会全体に大きく影響を与えていく。だから補助金がおりなくても、産前産後の支援に投資するんだってところが、今回一番腑に落ちたところです。
つるの/カフェの食事を子どもに無料で提供したり、駄菓子屋さんを地域に開放したり、それらも大切な投資のひとつですよね。この地で安心して子育てができれば子どもも増えるし、園の運営だって容易になる。まさにウィンウィンの関係ですよね。
柿沼/実は、この育児支援を始めようと思ったのは、卒園児が小学校で不登校になったことがきっかけなんです。すごくいい子で生活も安定した方で。それが5年生のときに、いじめが原因で不登校になった。そのときハッと気づいたんです。自分はその子の卒園式で「ここ(幼稚園)でいろいろなことを学んだから小学校に行っても大丈夫だよ」って言っていたのに、全然大丈夫じゃなかった。地域全体が安定しないことにはそういうことが起こるんだって。園のフレームの中だけではなくて社会全体に働きかけなければって思うようになって、ならば投資もありだな、と。みんなが気分よく過ごすための投資は、いつかは循環して戻ってくると思っていますから。


つるの/支援って、自分の手の届く範囲で取り組んでいくことも大切ですよね。あまり大きなビジョンを持ちすぎると、行動を起こす前に頭の中で破綻してしまうし。ここのように最初は小さいコミュニティーからスタートして、だんだん広がっていき、最終的に大きな流れになって子どもが増えていく。その感じを今日見られて、すごく自分の視野が広がった気がします。
大豆生田/地域全体で子どもを育てる社会づくりって、とかくビジョンが大きくなりがちで現実味がしなくなるけど、柿沼さんの話を聞いていると、先のビジョンよりは、”今“。「今、何が必要とされているのか」ということに、どう耳を傾けるかがすごく重要で、そこからアクションを生み出していく。読者のみなさんも、自分が何をできるか、どこから始められるか、改めて考えてみてはいかがでしょうか。今、できることって、いっぱいあるはずですから。

※取材時に撮影した動画(約40秒)が見られます。(←タップ or クリック)
文/松浦裕子 撮影/藤田修平
『新 幼児と保育』2025年夏号より
【関連記事】
大豆生田啓友先生×つるの剛士さん注目園訪問レポートシリーズはこちら!
・大豆生田啓友先生✕つるの剛士さん|注目園訪問レポート「大人と子どもがともに生きる力を養うコミュニティー」
・大豆生田啓友先生✕つるの剛士さん|注目園訪問レポート「地域全体で子どもの成長を楽しめる社会へ」
・大豆生田啓友先生✕つるの剛士さん|注目園訪問レポート「子どもを真ん中にした“まち”のコミュニティー」
・大豆生田啓友先生✕つるの剛士さん|注目園訪問レポート「子どもの夢を叶える保育園」
・大豆生田啓友先生✕つるの剛士さん|注目園訪問レポート「フレーベルのキンダーガルテンを目指す自然保育」
・大豆生田啓友先生✕つるの剛士さん|注目園訪問レポート「地域が支え、だれもが幸せになれる“こどもまんなかの暮らし”」
・大豆生田啓友先生✕つるの剛士さん|注目園訪問レポート「多様な人間同士が柔軟に寄り添う“インクルーシブ保育”」
・大豆生田啓友先生✕つるの剛士さん|注目園訪問レポート「子どもたちの自主性を尊重する体験型の学び」
・大豆生田啓友先生✕つるの剛士さん|注目園訪問レポート「子どもの主体性を育む“森の保育”」
・大豆生田啓友先生✕つるの剛士さん|注目園訪問レポート「僕らが考える『保育園の未来予想図』」
>>もっと見る